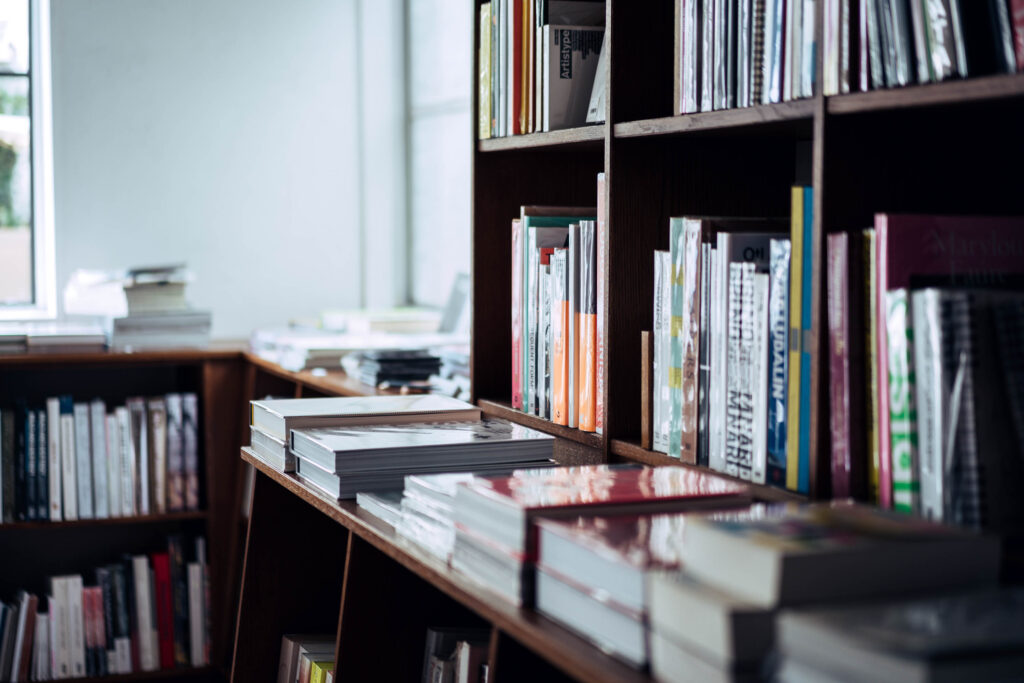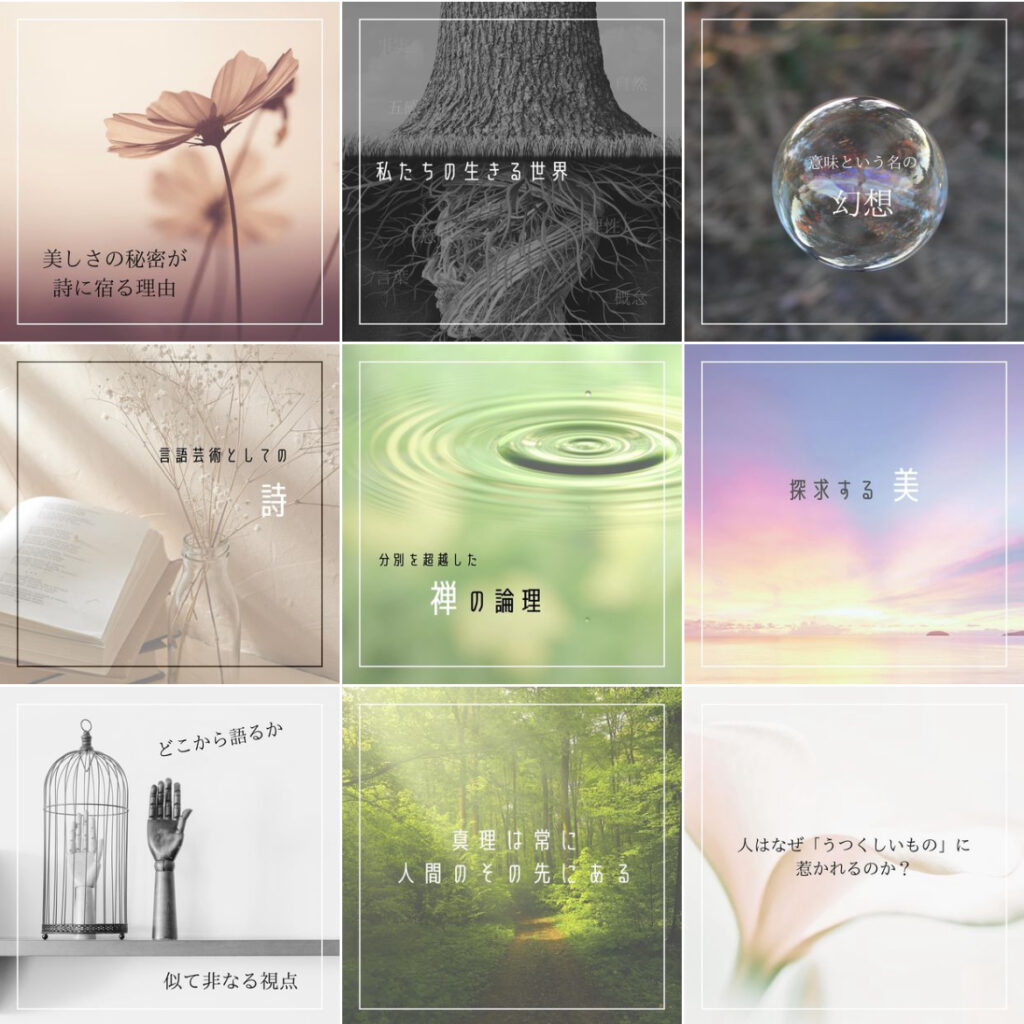人はなぜ「美しいもの」に惹かれるのか?
不思議に思ったことはありませんか?
人はなぜ「美しいもの」に惹かれるのか? 美しいと感じるものと、そうでないものとの違いは、一体なにか? と。
美の基準は人それぞれといわれますが、それでも多くの人を惹きつける美が存在する以上、主観的なものだけでなく、客観的なものもあるはずです。
例えば、花を見て美しいと感じる気持ちは、私たちの感性が受け取るもの、すなわち主観的に「感受されるもの」です。
しかし、芸術作品などがそうですが、同時に万人にとって、どの花が最も美しく感じるのだろうか、という疑問もわいてきます。そうなると美の感受は、概念的に「判断されるもの」とも言えます。
言い換えるならば、美の感受は主観的なものでありながら、同時に客観的な性質も併せ持つということ。つまり、両立不可能なものを可能にする。
これが美の持つ特異性であり、私たちが惹かれる理由でもあり、いまだ科学でも美しさの正体は解明できていません。
論理的や合理的であることの限界
現代では、論理的であることや合理的であることがもてはやされ、ロジックで詰めたり論破したりするようなあり方が、さもビジネスパーソンとして、大人としてあるべき姿であるかのように言われています。
もちろん、結果を出さなければならない責任ある立場の方にとって、合理性や論理性は大切です。それが不要になることは、これからもないでしょう。
しかし、「論理的な理解力や応用力、合理的であること」だけではAIが台頭する時代には、もはや不十分なのです。
実際、合理的・論理的な判断や科学的知識だけでは限界がある、と感じている方も多いことでしょう。
近年、美意識の水準が個人や企業の成果を左右すると言われるようにもなりました。多くの方がなんとなく気づき始めているのです。
芸術やアートなどクリエイティブな領域に限らず、ビジネスにおいても学問においても人生においても、非論理の領域が大切であるということに。
では、何を身につければよいのでしょうか?
機微を読み取る感性
私たちが今まさに取り戻すべきもの、それが「機微を読み取る感性」です。感性をみがく大切さを説く人はたくさんいらっしゃいますが、大事なのは「機微」です。
ここでいう「機微」とは、空気を読む力や忖度することではありません。人の心の動きという狭い範囲だけに対する洞察力のことでもありません。
心理学や脳科学などの科学的知見から理解できるものでもありませんし、個人の主観やセンスによるものでもありません。
「機微」とは、この世界と人間のあり方を示してくれる微かな機しのこと。
「機微を読み取る感性」とは、この世界と人間のあり方を真に理解するための力です。
その場の状況、雰囲気、空気感、表面に現れないもの、そして時代の流れ、それらの微妙な変化を読み取り応用するためには、文学や芸術などの美学的なセンスや感受性、そして知性がより求められます。
それはつまり、変化の時代にあっても変わらないもの、本質を見抜き、応用することができるということです。
美の哲学
「機微を読み取る感性」を研くのに最も適した学びこそ、「詩・禅・美」に代表される「美の哲学」です。
言語芸術と呼ばれる「詩」、分別を超越した「禅」の思想・哲学、非言語芸術の絵画を通しての「美」、そして西洋と東洋の哲学を織り交ぜた美の感受を通して、「機微を読み取る感性」を育み、世界の捉え方を変えていきます。
ビジネス上の問題も人生の問題も、白黒付けられるものなどない中で、自らが選び取るにふさわしい道を教えてくれるのも、こうした「美の哲学」の力といえましょう。
形而上の世界に触れる
実際、世界で活躍する真の成功者、有力者、実力者は、俳句を嗜んだり、美術館や音楽会などに足を運び、文学や芸術など形而上の世界に触れ、感性を研くことを大切にしています。
これは、なぜでしょうか?
美について考えることは、一見ビジネスや実利に全く関係のないことのように感じるかもしれません。しかし、普段自分がどのようなものに触れ、感性を研いているかが「生み出すものの質」を決めているかを深く理解しています。
自分のものの見方が変われば、世界や人間の捉え方が変わり、発想も変わってくるからです。
多くの人は、目に見えるわかりやすいものに飛びつきます。しかしそれらは、全て枝葉にすぎません。すべての物事の裏側には、一見すると「目に見えないものの本質」が常に存在しています。
すべての「目に見えるもの」は、何らかの「目に見えないもの」が変換され生み出されたものだからです。
ここで扱う「美学」は、最高抽象度の知。すべての根幹となる「源の知」であり、すべてのモノコトはこの知から生み出されます。
その一番上が変われば、一気に「知」の形が変わることは容易に想像できるでしょう。
また、哲、美、文といった形而上にフォーカスし、美の本質にせまるあり方によって、科学や実学など、実利重視の学びから逃れた、純度の高い「真の知性」に出会えます。

世界のアカデミズムに裏打ちされた真の美学
真美研究所では、世界のアカデミズムに裏打ちされた真の美学を提供いたします。
この真美研究所で扱う情報は、協力機関である東京官学支援機構(TASO)とTASOが主催する人文知普及と研究の会員制サロン東京美学倶楽部の資料をもとに作られております。
東京美学倶楽部は、最高学府と関わってきた経緯と実績を土台として、東洋知にも西洋知にもとらわれない日本知、メタアカデミズムを志向しています。メタアカデミズムは、あくまでもアカデミズムとの関わりを経由して辿り着いた領域です。
現在、国が認めている人文知(西洋哲学やリベラルアーツ)から、日本の未来のために国が庇護すべき真の人文知へ。
日本特有の美学、真美の探求のあり方を、共に学び、考え、伝える力を身につける。この使命の元に東京美学倶楽部は存在しています。当真美研究所の活動もその一環です。
大人の学びとは
今の日本には、実利・実用的な学び、即物的な学びばかりです。もちろん、そのような役に立つ学びも必要ではありましょう。
しかしながら、それだけでは人生というものはつまらなく、なにより人として生きる意味を失ってしまいかねません。物質的には豊かになったとしても、心は貧しいままです。
本来、価値のある学びとは、今の自分の理解を超えていると思えるような知に向き合うことです。
具体的に何が得られるのか、という問いから始まる学びは、自分の視座も世界の見方も変えてはくれません。理解できないからこそ、学ぶ意義と価値がある。
すぐに役立てようとしないことが大人の学びたる本質です。
考える力を磨く思考空間
大人の真の学びとは「教わる」のではなく、自ら「学ぶ」こと。つまり、考えること。
人は、情報量が多いと、正しい判断ができると思っています。しかし、真逆です。情報量が多くなればなるほど、実は思考力は低下します。
なぜなら情報と比例して考えるべきことが増えるからです。すると、問題が複雑化するため、判断が難しくなるのです。
思考は、思考をすることでしか研けません。「真に思考する」空間を定期的に設けることにより、本当の「考える力」がつきます。
また、知識として知っていても、体験が伴っていないと本当の意味で知ったことにはなりません。
そのため、真美研究所(シンビラボ)では、新しい情報や知識を頭に入れ理解しようとするのではなく、体得重視の実践的な演習を通して学ぶことを大切にしています。
こんな方におすすめ致します。
・知性と教養溢れる大人の女性としての美しさを求める方
・詩や文学、日本語の探究に興味のある方
・論理的な思考だけでは限界を感じている方
・新しい着想を生み出す視点を持ちたい方
・抽象的・本質的な学びに価値を持てる方
こんな方には向いておりません。
・すぐに結果が欲しい方
・知識を得ることを目的にしている方
・効率や合理性を優先する方
※ご入会は、随時受付ています。期間は、ご入会から1年間となります。
メンバーの属性
会社経営者、会社役員、起業家、外資系企業勤務、日系企業勤務、個人事業主の方など、業界業種も多種多様な方々に、ご参加いただいております。
世界のアカデミズムに裏打ちされた美の哲学を追求する上質な学び場

アクティブラーニング形式
体得重視の実践的な演習を通して、学ぶことを大切にしています。

最高知の普及に貢献
楽しく学びながら
「最高知の普及」に貢献できます。

上質な「思考空間」と「知的体験」
「真に思考する」ための上質な思考空間と知的体験を提供します。

真美研究所
美を探究することを通して「機微を読み取る感性」と「論理的思考力」を育むコミュニティ。

ミュージアム運営
文芸作品によるセラピーミュージアムというこれまでにない文芸展を運営。

ビジネスライセンス
美の哲学をご自身のビジネスに活かしたい方に向けたビジネスライセンスと会員証の発行。