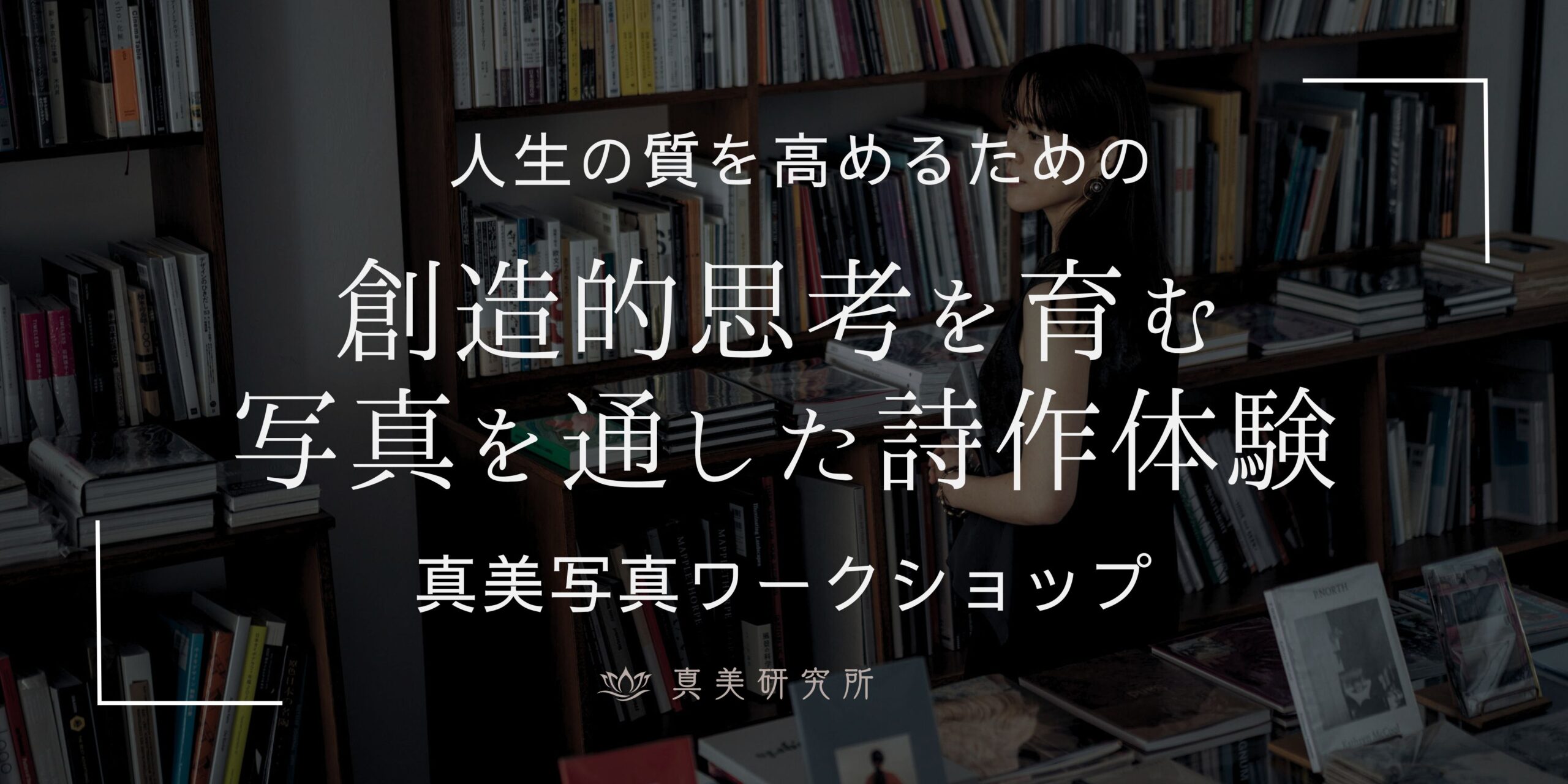
【日時】3月 4日(水) 13:00 - 15:00 残4
3月 7日(土) 13:00 - 15:00 残4
3月15日(日) 13:00 - 15:00
【場所】 ZOOMオンライン(顔出しをお願いしています)
【参加費】3,300円(税込)
※各回6名様まで、女性限定です。
女性経営者として。管理職として。チームを導くリーダーとして。
成果を出すことには、もう慣れている。判断すること、決断すること、言葉を選ぶことも。
それでも、ときどき「この感覚を、どこに置けばいいのだろう」と立ち止まる瞬間がある。
写真と詩が、あなたの中にある「美的知性」に、そっと触れていきます。その感覚はやがて、日々の決断や対話の奥行きとして、静かに滲んでいくでしょう。
真美写真ワークショップは、答えを出す場ではありません。問いの質を、もう一段深めるための時間です。
「足りない自分」を補う学びから、「すでにあるもの」を整え、研ぎ澄ます研鑽へ。
曖昧さを排除するのではなく、扱えるようになるための感性と思考を育てていきます。
感じて、言葉をうむ「真美写真」体験
判断や結論の前にある感覚を丁寧にすくい上げます。
目に見えるものの奥にある、まだ言葉にならない何か。それを、自分の言葉で捉え直す。そのプロセスこそが、思考と感性を結び直す実践です。
私たちが普段、目にしている世界や写真は、ほんとうに ”真実” なのでしょうか?
写真と詩は、普段、私たちが見えていない世界を、詩という言葉と感性で照らし出してくれます。
「真美写真」が見えたとき、 ”本当は自分がどんな世界を生きているのか” に気づき、絶対的な肯定感と安心感に包まれることでしょう。

詩とは「感性」だけでなく、「思考」を鍛えるもの
感性をひらくだけではなく、思考の深度そのものを高めたい。
そんな知的好奇心を持つ方にこそ、この詩的実践は力を発揮します。
詩は、感覚のままにとどまらず、それを言葉にすることで、思考を深め、世界や自分を理解していくための技法でもあります。
西洋・東洋・日本の知を横断しながら、詩を通して思索する。
それは、かつて哲学者や科学者たちも重んじた、もうひとつの知のあり方。
「そもそも哲学は、詩のように作ることしかできない」
── ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(20世紀最大の哲学者の一人)
判断・対話・直観 - ビジネスに不可欠な「感受性」を育てる
ビジネスの現場でも、直観力、判断力、対話力。それらすべては「感受性」という、見えない力に支えられています。
「感受性がなければ、判断はできない」
──アインシュタイン(理論物理学者)
詩を読むこと、詩を生むこと。詩に触れること。
それは、判断の根拠となる「感受性」を鍛える、実践的な方法です。
詩と写真を用いた表現は、論理や数字に頼らずに、「自分の言葉」で世界を読み解く力を取り戻す訓練でもあります。
単なる趣味ではなく、知性と美意識を育てる実践へ
このワークショップで扱う詩は、趣味として楽しむものや、感情の吐露を目的としたものではありません。
人生をもう一段深く見つめ、感じ、創りなおすための知的・感性的アプローチです。
感性を入口に、思考を研ぎ澄まし、言葉を通して人に伝わるかたちへと表現していく。
それは、あなたの内にある「見えない力」を、静かに目覚めさせていく時間になるはずです。
単なる自己表現にとどまらず、仕事や人生の意思決定を支える「洞察力」や「美的知性」を育む。
その本質に触れる体験を、ぜひ体感してみてください。
こんな方におすすめです
・微細な感覚や機微を言葉にする力を磨きたいと思う方
・日常の忙しさから離れて、自分と向き合う時間を持ちたい方
・創造的思考を育み、人生の質を高めたい方
・自分の言葉に自信が持てないと感じる方
・学びながら貢献するというあり方に共感いただける方
真美研究所は、 答えを与える場ではなく、 問いの中にとどまれる人のための場です。
「迷いは失敗ではなく、入口である」「分からなさは、成熟に向かうための通過点である」と考えています。

ワークショップの内容
【1】あなたの感覚が揺れる瞬間に出会う
まずは、何枚かの写真をみていただきます。
あなたの中に浮かぶ違和感や引っかかり、その小さな揺れが、今まで見過ごしてきた「真実」を映し出すレンズになるかもしれません。▶ 感じたことを、言葉にしてみる時間。あなた自身の“見る目”が立ち上がってくる瞬間です。
【2】言葉を超える言葉、日本語でしかたどり着けない世界へ
なぜ「詩」なのか?
ビジネス書でも自己啓発でもないこの方法に、本質を揺るがす可能性があるとしたら?西洋知・東洋知を経てたどりついた、「日本知」という新たな知のあり方をご紹介します。
▶問題を解決するのではなく、「なぜ悩むのか」その構造を見抜くための「考える力」が身につきます。【3】写真から、まだ言葉にならないものを紡ぎ出す
撮るのではなく、「観る」。
目の前の写真から広がる世界を、あなたの中にある言葉でつかまえてみてください。▶ あなたの感性が、静かに言葉になる瞬間を体験していただきます。
【4】“その先”へ
この体験のあと、「もっと自分の言葉を育てたい」「思考を深めたい」と感じた方へ、本格的な表現と思索の場をご案内します。
詩や写真の経験は不要です。評価や正解を求める時間ではありません。
他の参加者と比較されることはありません。安心してあなたの言葉を見つけてください。
参加者の声
・想像以上の深さに、心が動いた(40代、個人事業主・コーチ)
自分が想像していた以上に、深い内容で驚きました。同時に、「自分が求めていたのは、まさにこういう場だったのだ」と思いました。特に、「言葉によって感性が閉じられている」という言葉が、まるで自分のことのように胸に刺さりました。思考と感性のバランスを取り戻すきっかけをもらったように感じています。
・五感で感じた気づきと、人生を見つめ直す時間 (40代、自営業・製造業系)
ワークショップで、いかに自分の五感が詰まっているかに気付きました。少し緊張もありましたが(汗)、終わる頃には心が満たされていました。その後、お風呂でワークショップでの問いをいくつも思い浮かべていたところ、気付けば“とてつもない幸せ”に浸っている自分がいました。その瞬間、「もっと今を生きたい」と感じ、翌朝すぐに本講座への申し込みを決めました。哲学的な知識の学びは、本来、人間に備わっているものだと感じます。しかし、人生の中でそれに真剣に向き合う人は、とても少ないように思います。私自身も、日々の忙しさの中で、その大切さをつい後回しにしていました。私の人生にとって、きっとかけがえのない学びになる予感がしています。この出逢いを大切にしたいと思います。ありがとうございます。
・固定化された意味から、自由になる体験 (50代、会社員・カウンセラー)
私はずっと“言語化が苦手”だと思っていました。でも、実は“言葉”があることで、意味が固定されてしまい、自分の感覚そのものが鈍くなっていたのかもしれない、と今回のワークで気づきました。言葉の意味を手放したとき、逆に感覚が鋭くなっていくのを感じて、世界がひらけていくような、不思議な体験でした。今まで無意識に受け入れていた“常識” や “組織の枠” からも、一歩外に出られるかもしれないと感じました。
・作品に添える言葉をもっと深めたい (40代、抽象写真家)
抽象写真の作家として活動を続ける中で、自分の作品をどう言葉にし、どう伝えるか。その難しさに、ずっと向き合ってきました。作品に添える言葉をもっと深めたい。ただの解説ではなく、作品の奥行きや世界観を届けられるような言葉を紡げるようになりたい。そんな想いから、「詩」という表現にも惹かれ、参加を決めました。このワークショップでは、写真と言葉の関係性をあらためて見つめ直し、言語化の力を育てていくヒントをもらえた気がします。独自の表現を模索している方、感性と言葉の距離を縮めたい方におすすめしたい体験です。
・"正解"を探してしまう思考のクセに気づいた (40代、介護業界・管理職)
ワークをしながら、「正解は何かな?」と探してしまう自分の思考の癖に気づきました。つい“正しい答え”を見つけようとしてしまう自分がいる。あるものの中から、最適解を探そうとしてしまう自分がいる。普段は、そんなことにも気づかずに過ごしていたけれども、そこから自由になっていけることを少し体感しました。正解のない世界があっていいんだと感じられたことに、面白さを感じました。
・日本人に生まれてよかった (40代、フリーランス)
日本語の奥深さに触れ、日本人に生まれて良かったなと思いました。自分は言語化がすごく苦手だと思っていたんですが、実は、言葉をいっぱい持っていたことに気づかされました。言葉を知らない赤ちゃんだったらどんな風に見えるのだろうか、感じるのだろうか、と考えた時に、感覚はあるだろうと思い、そんなことを想像することも面白かったです。いろんなことを感じられた、とても良い時間でした。ありがとうございました。

主催:真美研究所について
このワークショップは、真美研究所が主宰しています。真美研究所は、「国ととともに人文知を守る」という理念のもと、哲学、美学、文学に代表される人文知の普及推進に取り組んでおり、この企画もその活動の一環です。
学びながら貢献するというあり方を志向する方と、共に学び、考え、伝える力を身につけるための会員制コミュニティです。
主宰者:豊田ふみこ
ビジュアルプロデューサーとして15年以上、経営者や起業家の「思想や美意識」を装いや写真に落とし込む仕事に携わってきました。
やがて、美しさを「見せる」だけでなく「観る」「感じる」「考える」ものとして問い直すようになり、哲学と美の探究へ。
現在は真美研究所を主宰し、詩と写真を通して感性と知性をひらくワークショップを展開しています。
詩と写真をとおして静かにひらく、もうひとつの世界と出会ってみませんか?
開催概要
人生の質を高めるための「詩と写真のワークショップ 」
【日時】3月 4日(水) 13:00 - 15:00 残4
3月 7日(土) 13:00 - 15:00 残4
3月15日(日) 13:00 - 15:00
【場所】 ZOOMオンライン(顔出しをお願いしています)
【参加費】3,300円(税込)
※各回6名様まで、女性限定です。

